イタドリの下処理や塩漬け保存方法などの食べ方をレシピといっしょに紹介します。
シャキシャキとした食感が人気のイタドリは、高知県民が大好きな春の山菜です。
郷土料理の達人たち(近所のおばちゃん達)に教えてもらったとっておきの方法ですので、私もじょうずに料理することできました。
イタドリを美味しく食べるためには2つのコツがあります。
- 下処理をする⇒あく抜き・えぐみを取る
- シャキシャキ食感を損なわないようにする⇒あまり煮過ぎない
塩漬けすると長期保存や冷凍保存も可能なので、お正月料理にも使えます。
- 失敗のない下処理のコツ
- じょうずな保存方法
- 家庭でできる簡単レシピ
皮の剥ぎ方もふくめ順番にご紹介しますね。
イタドリが好きすぎて長文になりますが、どうぞお付き合いください。
もくじ
失敗のない下処理のコツ

イタドリは下処理・下準備が大事です。
まずはイタドリの皮の剥ぎ方からです。
皮が残ると口当たりが悪くなります。
イタドリが手に入ったらなるべく新鮮なうちに皮を剥ぎましょう。
シーズンになると、高知県内のあちこちの道の駅、JA販売所などでも、袋いっぱいに入ったイタドリが100円~200円くらいで安く売られています。
道ばたでイタドリを採る時は、根元からポキンと折ります。
ちなみに、本気モードのおばちゃん達は、カマを持参して一気にイタドリを刈り、大きな袋いっぱいに採ってます。
長さは30センチ~50センチくらいがちょうどで、大きくなりすぎると固くなり、とう(薹)がたちます。
つまり食用に適する時期を過ぎてしまうんですね。
土や泥の汚れは、流水でささっと洗います。
せっかく採ってきたのに、私のように「あー、めんどくさー」と思ってそのまま放置しておくと、皮が剥ぎにくくなってしまいがちです。
イタドリは新鮮なうちが剝ぎやすいです。
もしも剥ぎにくくなっていても大丈夫です!
皮を剥ぎやすくする簡単な方法も教えてもらいました。
皮を剥ぐ作業

①皮を剥いでいきます。
下から上へ、太い方から細い方へと、ぴーーっと、面白いぐらいに剥げます。
ポキン、ポキンと適当な長さに手で折りながら、皮を剥いでいきます。
もしも皮が剥ぎにくい時は、ちょっとお日様に当てて温めてみて下さい。
大きなビニール袋に入れたままでもいいです。
あまり置きすぎてシナッとならない程度です。
または、さっとお湯をくぐらせると、皮が剥ぎやすくなります。
あったまる程度の温度のお湯です。
イタドリの皮は温めると、面白いほど剥ぎやすくなります。
②葉の先は取り除きます。
葉先は柔らかいので、そのまま天ぷらにして食べることができます。
また、さっと湯がいて、細かく刻み、塩味の菜飯(なめし)にすると美味しいです。
③10センチくらいの長さにに切ります。
シュウ酸を抜く作業(あく抜き)
皮を剥いだイタドリの茎を生のままかじると、酸っぱくてちょっとエグイ味がします。
この酸味の正体は、有機酸とシュウ酸です。
シュウ酸は、食べ過ぎると体内でカルシウムと結びつき、カルシウムを体外へ排出させる働きがあるそうですが、生で食べたとしても、大量でなければ大丈夫です。
では、イタドリのあく抜き(シュウ酸を取る)作業をします。
郷土料理の達人たちにお知恵を拝借しましょう。

イタドリのあく抜きは、どうしたらえいですか?
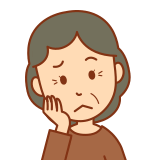
そやねー。
慣れてる人はさっとお湯を通してあく抜き。
慣れてない人は塩漬けが簡単よ。
なるほど、あく抜きは以下の2つの方法があるということです。
- さっと湯がいて水にさらしアクを抜く
- 塩漬けして水分と一緒にアクを抜く

1、湯がく方法と、2、塩漬けする方法とでは、使い分けはありますか?
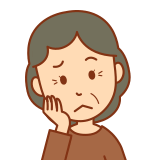
酢味噌やぬた味噌あえにして、すぐに食べたいなら、湯がいて水にさらす。
長期保存したいなら、塩漬けにしたらえいよ。
塩漬したら、水分と一緒にアクが抜けるんよ。
コリコリとした食感が残るし、長期保存できる塩漬けは便利よ。
なるほど、すぐにお料理に使うかどうかで、あく抜きの方法を変えられるということです。
1、すぐ調理するなら、湯通しをする
2、保存するなら、塩漬けする
お湯を使う下処理
では、湯通しして水にさらす方法で下処理してみましょう。
①イタドリの皮をはぐ
↓
②お湯をさっと通す
↓
③水ににさらす
という下処理で、イタドリのエグ味が抜けて、すぐにお料理に使って食べることができます。
ですが、お湯を使う方法は少々コツがあります。

お湯の温度って、どのくらいですか?
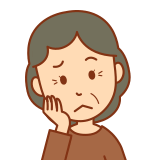
熱すぎず、低すぎず、触ると熱いくらいの湯やねー。
もう少し詳しく聞いてみましょう。

どんなふうに、お湯であく抜きしてますか?
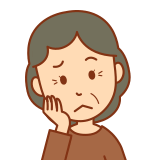
大鍋で湯を沸かしてさっと湯がいて、水にさらしたり
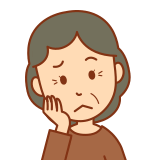
やかんに70度くらいのお湯を沸かして、上からかけて箸でコロコロまわす。イタドリの色が変わったら取り出して、水にさらす、という方法もあるわよ。

なるほど・・
ほかにも、お家によって、あく抜きの方法に違いがありました。
たとえばこちらの方法です。
1.台所の瞬間湯沸かし器の一番高い温度のお湯に漬ける。
↓
2.イタドリが浮かんでくるので、落し蓋(おとしぶた)をする。
↓
3.イタドリの色が変わったら取り出して、水にさらす。
お湯の中でイタドリの色が、濃い緑から薄い色に変わります。それがお湯から上げるタイミングです
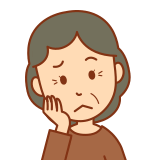
お湯から上げるタイミングは、イタドリの色が変わるから、分かるわよ。でも煮過ぎたらいかんよ。
どの達人たちに聞いても、共通する注意点は、
煮過ぎないこと!
煮過ぎると、いざ料理に使う時に、歯ごたえがなくドロドロとした感じであまり美味しくありません。
高温すぎても、低温すぎてもあくが抜けません。
70度~75度くらいのちょっと熱めの温度で短時間(10秒~30秒程度)です。
※イタドリの量や湯加減によっても変わります。

アクが抜けたかどうか、どうやったら分かるんですか?
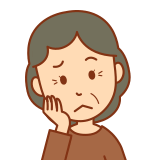
かじったら分かるわよ。
まー、やってみなさいや

かじったら分かる、なるほど・・
アクが抜けたか確かめるには、水にさらしたあと、少しかじってみます。
酸味が気にならないならあく抜き完了です。

それではやってみましょう!
イタドリを20本ほどゲットしました。
半分をお湯で、あとの半分を塩を使ってあく抜きしてみます。
まずは、少々コツが必要なお湯であく抜きに挑戦です。
イタドリの皮を剥いだあと適当な長さにポキンと折っておきます。
私は鍋に入るくらいの長さにしました。

皮を剥いだ生のイタドリは、鮮やかな色をしています。
青いイタドリと赤っぽい種類がありますが、一緒に調理します。

お湯を入れると、イタドリがぷかーっと浮かんでくるので、私は鍋のふたを逆さにして落し蓋かわりにしました。
うちの給湯器は、温度が60度くらい。ちょっと低めです。
そのせいか、4,5分ほどかかりましたが、イタドリの色が変化し始めました。
お湯の温度が高い場合は、もう少し短い時間でいけると思います。

この時点でかじってみると、まだ微妙にエグイです(^^;)
しかし、
☆イタドリの色が変わってます。
☆煮過ぎると食感がまずくなります。
「ここだな!」と思い、イタドリをお湯から出し、冷水へ漬けます。

ボールの水は3、4回ほどかえて、合計3時間ほど水にさらしました。
試しにかじってみましょう。

お!エグ味が抜けてます!
シャキシャキとした食感もじゅうぶんあります。
よしゃ、成功(^-^)v
3時間~一晩さらして、水から上げると、調理できます。
湯通ししたイタドリは、うすく斜め切りにして酢味噌、ぬた味噌、甘酢で食べるのが一般的です。
おすすめは、ぬた味噌和えです。
関連 イタドリ 食べ方 塩漬けなしの簡単レシピと 塩分ひかえめ冷凍保存の方法
上手な保存方法
塩漬けして保存する方法
では次に塩漬けして保存する方法を紹介します。
塩漬けすることでアクも抜けます。
冷蔵庫のない昔は一般的な方法だったそうです。
アク抜きと長期保存ができて一石二鳥ですね。

塩漬けと保存は、次のような順になります。
- 塩を振る
- 一晩軽く重石をして水分を出す
- 水分を捨てる
- 小分けして冷凍保存
一晩~二日かけて、じっくり水分を出すという達人もいます。
出てきた水分は捨てて、塩がついたまま、ジップロックに1回で使う量に小分けして、冷凍します。
塩漬けすることで、イタドリがシナッと柔らかくなり、塩のマグネシウムとシュウ酸とがくっつき、水分といっしょにアクが抜けるのです。

なるほど、お料理は化学ですねー。
塩漬けすると繊維が残ったまま水分が抜けるので、シャキシャキとした食感が残り、味もしみ込みやすくなります。
保存の目安
塩漬けしたイタドリは、長期保存が可能です。
目安は、半年~1年です。
春先に塩漬けして冷凍したイタドリがお正月料理に使えとっても重宝ですよ。
塩の量
塩漬けする時に、どのくらいの量の塩を使うのでしょうか。
達人たちに聞いてみましょう。

お塩の量ってどんくらいですか?
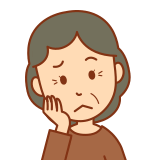
けっこうな量の塩で漬けても、水でさらしたら塩は抜けるきねー
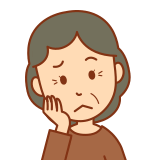
もちろん、塩が少なめでもできるよ。
きゅうりの酢の物を作る時ぐらいの塩をパパッと振って、重石をして水分を出すとえいね。
なるほど、こんなに大量の塩入れたら辛いじゃん!と思っても、使う時に水にさらすので、塩は抜けます。
冷凍庫がない昔は、塩漬け保存が主流でしたが、今はどの家庭にも冷凍庫があります。
塩控えめで重石をして水分を出し、すぐに冷凍保存をするのです。
薄塩(うすじお)で冷蔵で保存する場合は、1~2日以内にお料理に使いましょう。
塩抜きの目安
最後に、冷凍保存から出して調理する前、水にさらして塩抜きする時間と目安を聞いてみました。

塩が抜けたかどうかは、どうやって分かるんですか?
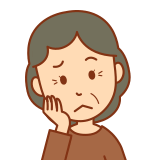
何回か水を替えて、一晩水にさらしたら塩は抜けるわよ。
かじったらみたら分かるわよ。

かじったら分かる・・確かにそうですね、ハイ
塩抜きの目安は、量にもよりますが、一晩~1日くらい。
かじってみて「うん、塩が抜けたな」が目安です。
最近は、皮をむいて塩漬け冷凍保存されたものも市販で手に入ります。
高知で食べたイタドリをもう一度食べたいと思われる県外の方におすすめです。
家庭でできる簡単レシピ
それでは、家庭でできるイタドリの簡単レシピを紹介します。
ご飯がすすむ イタドリの油炒め

家庭で簡単にできる定番レシピは、お肉(鶏肉や豚肉)と炒めて、砂糖、醤油で甘辛く味付けするお料理です。
イタドリは油と相性がいいです。
仕上げにごま油を使うと、ほんのり香ばしくなりますよ。
ちなみに、うちは鶏肉とちくわを入れて炒めます。
シャキシャキとした歯ごたえと和風の味付けで、ご飯がすすみ、お弁当のおかずにもいいですよ。
材料
【イタドリの油炒め・材料】 4人分
| 塩抜きしたイタドリ | 300グラム |
| 鶏肉 | 100グラム |
| サラダ油(ごま油も可) | 大さじ2 |
| だしの素 | 少々 |
| 砂糖 | 大さじ1(お好みで) |
| 醤油 | 大さじ1(お好みで) |
| みりん(酒も可) | 大さじ1(お好みで) |
作り方
作り方を紹介します。
①塩漬けした冷凍のイタドリは、前の日から水でさらします。水は3回替えるくらい、塩がきつければ、ちょびちょび、水道の水を出しながらさらして、かじってみて「あ、塩抜けたかな?」が、目安です。
②イタドリの長さも好みですが、ひと口大の5センチくらいが適当です。
③鍋に、油を入れてお肉を炒めます。お肉の代わりに、油揚げや、ちくわでもOK.
③次に、イタドリを入れます。
④だしの素、砂糖、醤油、みりんを入れます。
⑤一煮たちして、イタドリに味がついたら出来上がり。
煮過ぎるとイタドリがどろっとして、歯ごたえがなくなります。
仕上げに、ゴマ油を入れると香ばしくなります。
ちょっと、ピリ辛にしたい人は、七味唐辛子をふりましょう。
甘酸っぱいイタドリジャム

なんと!イタドリは、ジャムにもなるんです!
私も作ってみました。
作り方はとっても簡単で、面倒な下処理や塩漬けも必要ありません。
イタドリジャムの作り方をこちらで紹介していますので、ぜひご覧ください
関連 イタドリ ジャム 簡単レシピ!甘酸っぱさが魅力の意外な味
イタドリの思い出

食べられる山菜のイタドリは、昔の子どもたちのおやつ代わり。
シルバー世代のおじさん方は「おやつのなかった昔は、イタドリを採って皮をはいで、塩つけて食べたもんだ」と言ってます。
今も、学校からの帰り道、道草をしながらイタドリを採るのが、子ども達の楽しみです。うちの子も、小学生の頃は、「お母さん!イタドリ採ってきたよー、おかずにしてー!」と、ニコニコ顔で、5,6本手に持って帰ってきてました。
ただし、イタドリ好きの高知県民は、イタドリが生えはじめると、我先にみんなこぞって採りに行きますから、早い者勝ちですね!山菜のふきのとうやタラの芽も同じく早い者勝ちです。
長期保存の場合は塩漬けの冷凍がおすすめで、高知では春に採ったイタドリを、冬まで冷凍し、お正月のお料理によく使ってます。塩漬けしたイタドリは、シャキシャキとした食感と歯ごたえがあって、めっちゃうまいんだなー。
イタドリからできる製品
サプリメント
お日様の匂いと、懐かしい草の香り、しょっぱい味がなんとも魅力的な植物イタドリ。
北海道から西南の日本全国、台湾などの東アジアに広く分布し、どこにでも生えています。
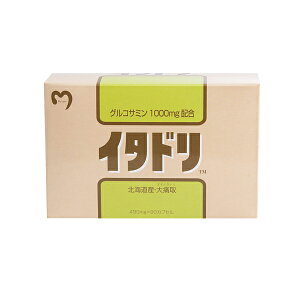
イタドリ 箱なし(90粒 約30日分)マイケア グルコサミン コンドロイチン コラーゲン 大痛取
イタドリ茶
高知市内の鏡(かがみ)地域では、面倒な皮はぎが簡単なイタドリの品種を栽培して、食品として加工する試みがされています。
最近の研究では、イタドリの葉にダイエット効果のあるポリフェノール成分「ネオクロロゲン酸」が大量に含まれていることが分かりました。
イタドリの葉が全国のお茶の間に知られる日も近いかもしれないと、私は密かに期待しています。
イタドリは高知の郷土料理に欠かせません。子どもからお年寄りまで人気の「イタドリの特集」です。
関連 【特集】イタドリの食べ方 レシピ 下処理から塩漬けの保存 丸わかり編










