おいしい金柑の甘露煮の作り方レシピです。
金柑は小さな実のわりには種がたくさん入っていて種取りがめんどうだったり、種類や熟し具合によってはピリピリとした苦味が残ることもあります。
- へたや種の取り方
- 苦くならないコツ
- 保存期間
- アレンジレシピ
を、料理の得意な達人に教えてもらいました。
もくじ
ヘタの取りかた

まずは、金柑のへた取りです。
木から もいで採る場合
金柑の木にはトゲがあるので、厚手の手袋をして実をとります。採る時に、くいっと引っ張ってヘタ(蔕)の部分が残らないように取ると、あとが楽です。
ヘタが残っている場合
ヘタの部分が残ったり、お店でへたのある金柑を買った場合、爪で取るのは痛いし、爪楊枝(つまようじ)も弱く、すぐに折れてしまいます。
この場合、じょうぶな竹串でヘタの部分をほじるようにして取ります。
完全に取らないと口に残るので、きれいに取っておきましょう。
種の取りかた
次に、種の取り方です。
私は金柑ジャムを作ろうとして「金柑を煮た後にザルで濾したら簡単かな?」と思いやってみましたが、金柑の中の白い部分、じょうのうの繊維はけっこう強くて、種と分けるのが難しかったです。
半分に割ったりスライスして種を取ることも試してみましたが、
一番きれいに種が取れた方法は、
切れ目を入れて竹串で種を取る方法でした。
これなら、まん丸いきれいな形の甘露煮ができます。

金柑に切れ目を入れて種を取ってみましょう!
①金柑をきれいに洗う。
まず、生の金柑をきれいに洗い水分をふき取ります。
②金柑をたてにし切れ目を6筋くらい入れる。

つぎに、金柑をたてにして切れ目を6筋くらい包丁で入れます。
金柑の皮は思ったより硬いです。
また、種の入っている白い部分もわりと強いです。
上下を残して切れ目を入れますが、気持ち深めに切れ目を入れます。

が、思い切り過ぎたり、切れ目を8筋とかにすると、上下が切れてしまい、湯がくと、タコの足ウインナーみたいに広がってしまいます。

失敗しちゃった分は、あとでジャム(マーマレード)にしましょう。
③竹串で切れ目からホジホジして中の種を取り出す。

つまようじは弱いので、竹串を使います。
種は金柑1個あたり、5個から8個ほど入っています。多少残ってもだいじょうぶです。
中のじょうのう部分は、思ったより強く手ごわいですが、慣れるとちゃっちゃと取れます。

湯がいて煮こぼしした後に、種を取る人もいますが、私のおすすめは生のまま種を取るです。その方が簡単だと思います
苦味の取りかた
種取りがクリアできたとして、次は、この苦味をどうするかです。
達人たちに聞いてみると、お家によってそれぞれ苦味・渋味を取る方法がありました。
1、水に漬けて苦味を取る方法
種取りや煮こぼしなどの下処理をする前に
一晩、水に漬けて苦みを取る方法です。
2、煮こぼしをして苦味を取る方法
煮こぼしをして苦みを取る方法もあります。
煮こぼしとは、グラグラと沸いたお湯で1.2分サッと湯がいてその煮汁を捨てて、また新しいお湯でゆがく作業のことです。茹でこぼしも同じ意味です。
種を取ったあとに、
1、お湯で金柑を煮て、煮こぼしをする工程を、2回~3回繰り返す。
2、煮こぼしした後に、1時間くらい水に漬ける。(一晩漬ける人もいます)
と、念入りに下処理をするお家もあります。

私は、切れ目を入れて種を取り、それから煮こぼしを2回、1時間水に漬けて苦みをとりました。
金柑の苦味の正体は?
この苦味の正体は、「ナリンギン」という成分です。柚子や文旦、グレープフルーツの果皮にも含まれている刺激の元となっている成分だそうです。
「ナリンギン」は、血中の脂肪酸を分解したり、抗アレルギー作用や免疫力を高めるといった、体にも良い成分です。
しかし、鋭い針状の結晶をしているため、口の中に入ると粘膜が刺激されてピリピリとしてくるのだそうです。
苦味は「ナリンギン」という成分の作用によるものですが、金柑は通常、生でかじっても味を楽しめる果実ですから、まずは生で食べてみて、美味しいものは甘露煮にしても美味しいと言えます。
また、成り始めの頃よりは年明けの方が甘くなります。
ですので、木の種類にもよるけれど、苦味は熟し具合によっても差があるということになります。
生でかじった時に苦みが少ない金柑なら、煮こぼし1回でも大丈夫です。
金柑の甘露煮の作り方
A、水で煮るレシピ
下準備として、
★種取りは王道の切れ目&竹串ほじほじ
★苦みを取るために煮こぼし2回とそのあと1時間水に漬ける
という作業がおわりました。
それでは、定番の水で煮るレシピで金柑の甘露煮を作ってみましょう。
材料と用意するもの

| 金柑 | 500グラム(30個くらい) |
| 砂糖 | 250グラム(目安は、金柑の重さの50%~70%でお好みの量) |
| 水 | 適量(お鍋に金柑を入れて、ひたひたになるくらい) |
| 酢 | 大さじ1 |
| ビン | あらかじめ煮沸消毒しておく |
作り方
種を取り、苦味を取るための煮こぼしなど下処理をした後の作り方です。
- 鍋に金柑を入れ、ひたひたになるくらいの水を入れる。
- 沸騰したらお好みの砂糖、お酢大さじ1を加え、弱火にして煮詰める。
- 時々、鍋をコロコロっと回す。
- 金柑の皮がやわらかくなり、トロトロっとしてきたら出来上がり。
- ふっくら感をキープするために、鍋が十分冷めてから蓋(ふた)を取る。
- 煮沸消毒したビンに入れて保存。

★煮詰める時間は?
金柑の皮の固さや量によっても違いますが、弱火にして30分~40分で出来ました。早く食べたくて、そこで火を止めましたが、もう少し煮てもいいかもしれません。何度か火を止めて煮詰めるを繰り返し柔らかーく作る人もいます。
★お砂糖の量や種類は?
白砂糖やグラニュー糖を使う人が多いです。量は長期保存するためには、金柑の50%以上は入れるようです。お砂糖+はちみつで作るもOK。
★お酢を入れるの?
お酢を入れると、長期保存しやすく、お砂糖の量を控えめにすることができるそうです。お家によって、お酢の量もたくさん入れる人、仕上げに大さじ1杯入れる人、また、お醤油を仕上げに少し入れるという人もいます。うちは、仕上げに大さじ1杯入れる派です。

種を取らず・煮こぼしなしで作る方法
職場でどうやってみんな金柑の甘露煮を上手に作ってるんだろうと聞くと、早速料理上手なIさんのお母さんから回答がきました。
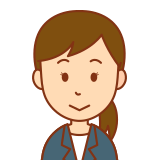
焼酎で煮れば、煮こぼしなしで簡単にできるよ。

種はどうやって取るんですか?
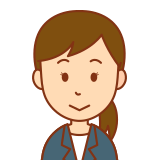
種は取らないよ、うちはそのまま煮るから。

え?種、取らなくいいんですか?
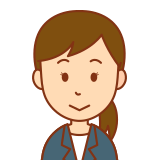
うん、取らないよ、そのまま。
めんどうな下準備がいらないということです。
それでは、種取りなし・煮こぼしもしない「焼酎で煮る方法」で金柑の甘露煮を作ってみましょう。
B、焼酎で煮るレシピ

材料
| 金柑 | 1キロ |
| 白砂糖 | 500グラム~1キロ(金柑の重さの50%~70%) |
| 焼酎(度数は20度以下) | 200cc=鍋に入れた金柑がひたひたになるくらい |
※初めて作る場合は上記よりも少量で試してみて下さい。
【注意点】
焼酎の量は少なすぎると、焦げたり、仕上がり時に金柑がしぼみやすくなります。
金柑は酸が強いので、アルミの鍋は避けましょう。
作り方
焼酎で煮る作り方です。
- 金柑をきれいに洗う。
- へたを取る。
- 鍋に金柑を入れ、金柑がかぶるくらい焼酎(20度)を入れる。
- 強火で一度沸騰させる。
- 沸騰したら、弱火にして40分煮る。
- 40分経ったら、白砂糖を入れて、弱火でまた40分煮る。
- 泡がぶくぶくと立ってきたら出来上がり。
- すぐに、取り出して食べたい衝動を抑えて、鍋が十分冷めてから蓋(ふた)を取る。
★焼酎の度数は?
20度です。うちは旦那さんが飲んでいる麦焼酎を使いました。
★出来上がりの目安は?
金柑の皮がだんだんと薄くなり、種が透けて見えてきたら、出来上がりです。
★焦げない?
あんまり煮詰めすぎると、焦げてくるので注意です。
★出来上がった時に丸いふっくら感を残すには?
・煮る前に、竹串で3か所くらい金柑に穴をあけてから煮る。それでもしぼむ時もあります。
・なるべく、ふたを開けない、または開けても短時間にしておく。蓋を開けると蒸気が逃げて金柑が急にしぼんでしまいます。
「焼酎で煮る」レシピでは、最初に40分、砂糖を入れて40分と長時間・弱火で煮ています。出来上がりを味見すると分かりますが、高温の焼酎で煮るため、種まで柔らかくなって食べることができます。
焼酎で煮る作り方なら、種取りも湯こぼしも不要!苦味もなく一石二鳥です。
アルコールも飛んでいるので、それほど気にはなりません。
ただし、
- 金柑の種類や実によっては皮が厚く種が透けて見えなかったり、種が硬い種類もあります。
- 焼酎で煮るため高温であっつあつになります。味見する時は、やけどしないように気をつけて下さい。

水で作るレシピはスタンダードな甘露煮です。
焼酎で煮るレシピはほんのりお酒の香りのする大人の味です。
甘露煮の保存期間
金柑の甘露煮は冷蔵庫で保存します。
- 砂糖が金柑の50%以上の分量なら、約1ケ月
- 砂糖が50%以内なら、2、3週間程度
が保存期間の目安です。
アレンジレシピ
金柑の甘露煮は、パウンドケーキやパンにして焼いても美味しいですね。
金柑の効用
幸運をもたらす縁起の良い金柑料理は、
- 風邪予防や
- 冬の栄養補給
- お正月のおせち料理にも使える
食べなきゃ損の、栄養満点の食べものです。
乾燥する冬、のどのイガイガ対策や風邪対策には、だんぜん金柑です。
皮ごと食べる金柑には、ビタミンCやカルシウムが多く含まれていて、昔から咳止めや、のどの痛みをとるお薬として使われてきました。
冬至に食べる理由
特に冬至には、「きんかん=金柑」とか、「なんきん=南瓜(かぼちゃ)」とか、「ん」が2つ付く食べ物を食べると風邪を引かないと昔から言われます。
まとめ
以上、金柑の甘露煮を作るときの、へた取り・種取り・苦味の取り方と、甘露煮レシピでした。
こうしてみると、金柑の甘露煮も「うちの甘露煮はこれだよ!」って感じでお家によってそれぞれです。家庭の味が美味しい決め手ですね。小さな実のわりには栄養満点。金柑ってホント可愛いくて私も大好きです。
甘露煮を作ってみたいけど、うちには金柑の木も無いし、近くに売ってるお店も無いなーという方。インターネットでも、無農薬や甘い種類の金柑が手に入ります。
たくさん出来たら、おすそ分けできる小さめのビンが便利です。
その他の金柑レシピ

金柑の甘露煮ができたら、次はあざやかな色が人気の金柑ジャムを作ってみませんか?
種の取り方や苦みの取り方のコツを押さえれば、とてもおいしく出来上ります。
風邪予防にも喉が痛い時、そして美肌効果や動脈硬化などの予防にもいい「金柑のレシピ特集」はこちらです。
関連 【特集】金柑 甘露煮 レシピ 人気のジャムやピールも作ろう!


金柑の実がたくさん手に入ったら、金柑酒を作るのもおすすめです。
ホワイトリカー(焼酎)を使えば、2週間から1ケ月で、苦味のないスッキリとした金柑酒が漬け上がりますよ。
作り方はこちらです。










